レクチャーシリーズ「批評と芸術」
第一回「変異する文化史」

レクチャーシリーズ:批評と芸術
第1回「変異する文化史」2024年2月3日(土)14:00〜17:30
実施レポート
文=沢山遼|撮影=稲口俊太
2024年2月3日、文化庁アートクリティック事業の若手批評家によるレクチャーシリーズの第一回目が開催された。登壇者は、きりとりめでる、gnck、仲山ひふみの各氏。当日は、三名のレクチャラーによるレクチャーとディスカッションが行われた。
デジタル写真論研究やメディアアートをベースに多くの展覧会レビューを執筆するきりとりめでる氏は、アナ・チンの『マツタケ 不確定な時代を生きる術』を参照しながら、展覧会レビューや批評全般の執筆を不確定的な要素の強いマツタケの生産と採集になぞらえ、現代の情報化社会、資本主義社会における批評のありかたを分析した。

さらに個人が不安定化、流動化した資本主義的な社会のなかで、感情の鈍化、注意の分散、対象の類型化がたえず行われる状況下において、その都度例外的で個別的な事象と結びつく作品の可能性を記述するための批評の方法論についての検討が行われた。そこで参照されるのが、写真史家ジェフリー・バッチェンが推進したヴァナキュラー(vernacular)写真研究の方法論である。きりとり氏は、批評対象に概念的同一性を与えてきた枠組みを考え直し、作品毎の美術史を立ち上げるための装置としてのヴァナキュラー文化研究の有効性を検討した。

批評的言説の蓄積とグローバルなアートシーンとのネットワーク構築を目指し、文化庁アートクリティック事業では、国内の有望な批評家を海外に派遣しています。
この事業は、美術分野における批評活動の拡大と国際的な交流の促進を目的としています。派遣された批評家は、派遣先地域の社会的・文化的文脈やアートシーンとの結びつきを学び、批評的思考を磨くとともに、現地の専門家とのネットワークを築くことを目指します。批評的言説の蓄積とグローバルなアートシーンとのネットワーク構築を目指し、文化庁アートクリティック事業では、国内の有望な批評家を海外に派遣しています。この事業は、美術分野における批評活動の拡大と国際的な交流の促進を目的としています。批評的言説の蓄積とグローバルなアートシーンとのネットワーク構築を目指し、文化庁アートクリティック事業では、国内の有望な批評家を海外に派遣しています。

批評はいつでも、現在という時空間への拘束から思考を解き放つ特権的な事件として存在します。
批評とは、あるものの正しさをことさら言い立てるものでも、特定の立場や利害を代弁するものでも、価値判定のための弁明でもなく、つねに、新たな思考を立ち上げる特殊な場の発明と創造に関わっているからです。
本レクチャーシリーズは、未来の芸術批評を担う新たな才能とともに、そのような批評の場を召喚する試みであり参加レクチャラーがそれぞれの関心に基づいた発表を行い、現在どのような問題が批評的な課題として抱えられているのかを発表し、議論を促進します。個々の関心領域で抱える課題と展望をめぐる議論から、言説を軸とした専門家の交流やネットワークづくりを活性化させることを目指します。
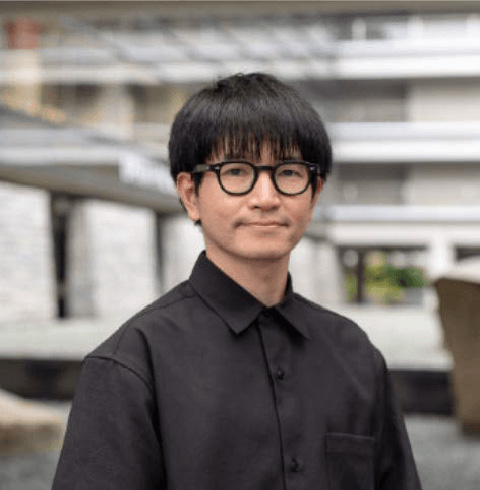
ディレクター
勝俣涼 Ryo Katsumata
美術批評家、武蔵野美術大学美学美術史研究室准教授
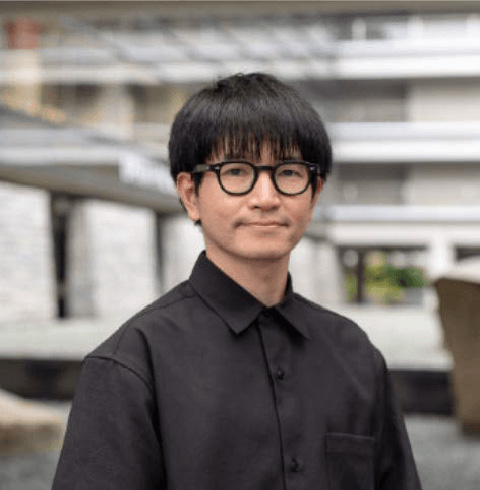
ディレクター
勝俣涼 Ryo Katsumata
美術批評家、武蔵野美術大学美学美術史研究室准教授